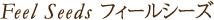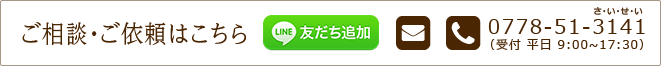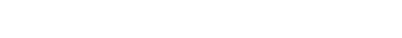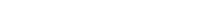お知らせINFORMATION

値段はどうやって決まるの?
いつも めがね修復・復刻保存館 フィールシーズをご利用いただきありがとうございます。
今回は、めがねの値段(価格)の決まる仕組みについて紹介します。
先に答えを言ってしまいますと、現在販売されているめがねの価格のほとんどが、「積み上げ算」で決まっています。
この積み上げ算とは、ひとつひとつの工程にかかる金額を足した合計金額、ということになります。
他業種で言えば、車の車検整備費などを連想してもらうと 分かりやすいでしょうか。
この価格設定方式は 産地さばえに古くから根付いており、100年以上前の歴史を紐解く事にもなります。
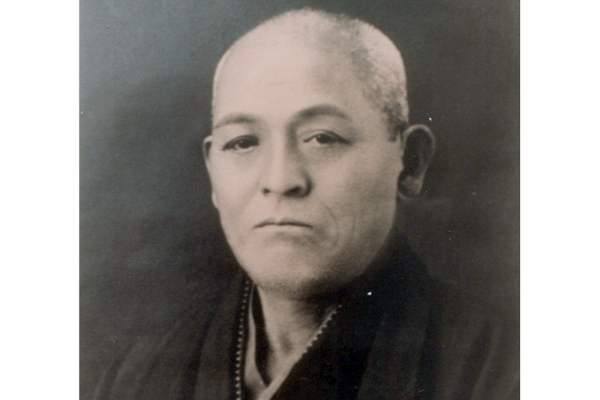
故 増永 五左衛門 氏
増永眼鏡㈱ 蔵
世界3大メガネ産地のひとつ、ここ 鯖江では、めがねを一貫生産出来る工場がほとんどありません。(プラスチックフレームは別)
これは、鯖江にめがね生産が根付く基礎を作った、故 増永五左衛門 氏がめがねの製造を分担させて互いに競わせた、という流れが今に残り、高品質のめがねが分業にて作られる礎となったものです。
結果、いくつもの工場の分担で出来上がったパーツなどを、また別の工場で組み上げて一つのめがねが出来上がり、各工程(工場)ごとに掛かった金額が足され、その合計がめがねの値段に直結するようになりました。
大手自動車メーカーなどでもよく聞く、下請け・孫請け・曾孫請け、のような体系をイメージしてもらうと分かりやすいでしょうか。
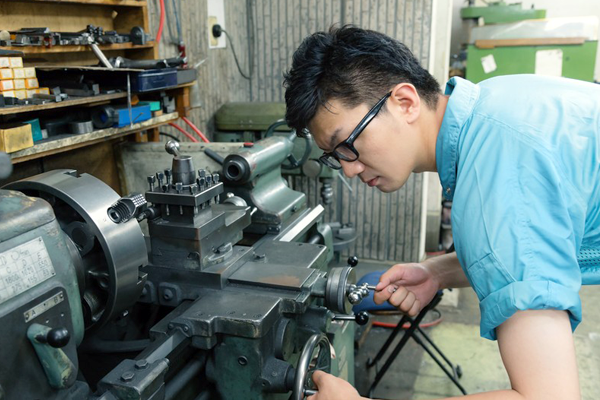
機械によっても差が出ます
写真はイメージ
また、材料によっても価格の違いはありますが、その材料で製造する為の機械や加工の難易度、工程数によっても大きく変わってきます。
金属(特にチタン)を加工する為の機械はとても高く、~千万円するものも珍しくなく、それらを扱う場合当然加工費が上がります。
それらの機械は、一つの同じ作業を長く稼働させ、数多く作るほど 加工費を抑える事が出来るので、製造数(注文数)が多いほど1枚の単価を低くできる訳です。
一般的にメガネが出来上がるまでに、セルフレームは約170工程ほど、現在のメタルフレームは 約200工程以上とも言われています。
主に中国や韓国などで製造され、数多く見掛けるウルテム・TR-90などは、型に樹脂を流し込んで製造される「成型」の為、多くの工程が簡略化され、人件費も日本国内よりも低く、安価に仕上がります。(人件費は地域にもよります)
これら様々な背景から、国産のチタン製メガネは価格が高くなる傾向になり、中国や韓国製の軽量樹脂フレームは 安価になりがちなのが一般的です。

ぜひ ショップでチェック!!
ここメガネ産地のさばえでは約6000人がメガネの仕事に携わっています。
余談ですが分業の中には、ネジを取り付けるだけの作業、などもあります。
一言でネジと言っても、セルフレーム、チタンフレーム、ツーポイントでは手間が全く違う為、工賃は10倍以上の差があったりもします。
メガネ業界では、販売価格を先に決め、その値段で仕上がるように調整振り分けしていく、という設定方法があてはめにくい図式なのはご理解頂けましたか?
まとめると、めがねの値段は 材質・工程数・製造数、人件費、その他すべての積み上げ算で決まっているのがほとんど、という事になります。
皆さんもお近くのショップなどでメイド イン ジャパンの高級チタンフレームの価格と品質・他との違いをぜひチェックして見てください。
さばえの技術の結晶「高額である理由」がそこに見て取れますよ。
以上、めがねの値段の決まり方、でした。