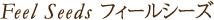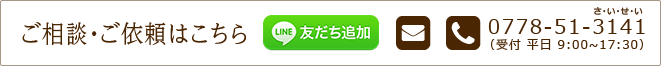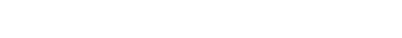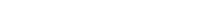お知らせINFORMATION

9月13日付 福井新聞より
いつも めがね修復・復刻保存館 フィールシーズをご利用いただきありがとうございます。 今回は当店とコラボレーションして頂いている越前漆器の産地の中でも数の少ない沈金師、二代目 冨田 立山(とみた りつざん)さんにスポットを当ててご紹介します。 以前にも大変腕の立つ職人さんとご案内しましたが、なんとその後すぐに地元福井では9月14日放送分の二代目和風総本家に取り上げられご出演されていました。 驚くことにその前日9月13日には地元福井新聞に掲載されるという、2日連続のメディアに登場されるご活躍ぶりです。 このご活躍ぶりにはコラボしている当店も嬉しく、また誇らしくなってしまいました。 また、このお知らせを作成中にも地元福井のTV局にて、後日紹介される事がわかり、もう言葉が見つからない状態です。 大変お忙しい方ですので正直コラボしていただけたのも奇跡のような話です。 インターネット上では冨田立山と検索してもらえれば、先代、二代目ともに力作が掲載や販売されており、誰でも簡単に作品を目にすることが出来ます。 当店の特殊加飾で沈金を選択していただくと、職人冨田氏の繊細かつ緻密な彫りを身に着けていただける訳です。

鷹 越前和紙とのコラボ作品
左の作品は上記新聞掲載の冨田氏の作品です。 これは9月21日から開かれている テオ・ヤンセン展の会場「サンドーム福井」の中で同時期に開催されている 世界の漆芸作家と越前和紙のコラボ作品展 の会場内で展示されているものを写してきました。 この作品は下地に越前和紙を使い、鷹をかたどった漆塗りの板を和紙に貼り付け作られたもので、漆塗りの板に細かく沈金が細工してあります。 当店のめがねにもコラボしていただいてますが、越前和紙など様々な分野に果敢にチャレンジし、ありとあらゆる可能性を見い出す多才な先駆者でもあります。 和風総本家の中では、彫りの作業は周りが静かになった夕方や夜から始めることが多いそうで、基本的にはその晩中に彫り終える、と語られていました。 いったん彫る刃を止めて翌日作業になると、力加減が変わってしまい彫りの深さや表現が違ってしまうからだそうです。 なので、作業を始めると明け方まで彫り続けることもあるとか。 沈金は奥が深く、根気のいる作業なんですね。

プレート 仁王像
左はプラスチック製メガネの材料、セルロイド板に彫ってもらった力作、仁王像です。 スマホやタブレットでご覧の方はぜひピンチアウトして拡大してご覧下さい。 黒色のセルロイド板のサイズは約10㎝×8㎝ほどです。 この作品も点彫りという技法によって作られ、彫刻刀のような刃先でセルロイド板の上を刺すように彫り込んでいきます。 この彫り具合だけで陰影などの表情を作るまさにプロの手仕事です。 彫ってくぼみを付けた後は漆を塗り、漆が乾燥する前に金粉を振りまき、その粉の自重によって漆の下に沈んで行く訳です。(今回はプラチナ粉を使用) 金粉などを振りまいた後、布などを使いはみ出した粉を拭き取りながらくぼみに刷り込んでいき漆を乾燥させます。 金などを沈ませて色柄模様を作る技法から沈金と名付けられたそうです。 また、漆の特性は不思議で、熱や光では全く乾燥しません。 漆は木の樹液なのですが、湿度により乾燥しますので、湿度が高い梅雨が一番早く乾燥する季節になります。 不思議ですね、誰が最初に気づいたのか、先人の知恵は大したものです。 漆器を営む職人さんの工房では、漆を乾燥させる場所 むろ と呼ばれる乾燥室がありますが、霧吹きでむろ内を十分湿らせて漆を乾燥させる技法が今でも使われています。 越前漆器は日本最古、1500年前の古墳時代末期にはじまり今に至ります。 古きいにしえの技法を現代に伝え、先の未来へも伝承し続けていく越前漆器の加飾、沈金・蒔絵をぜひあなたのメガネにも。